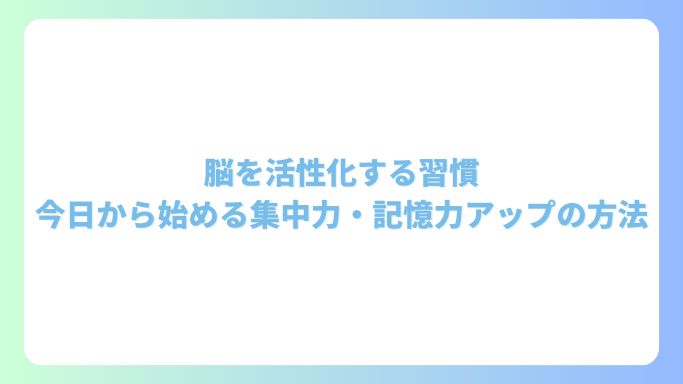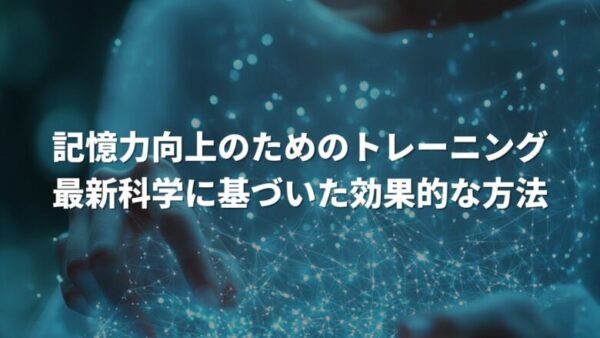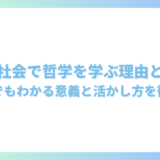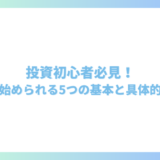1.はじめに
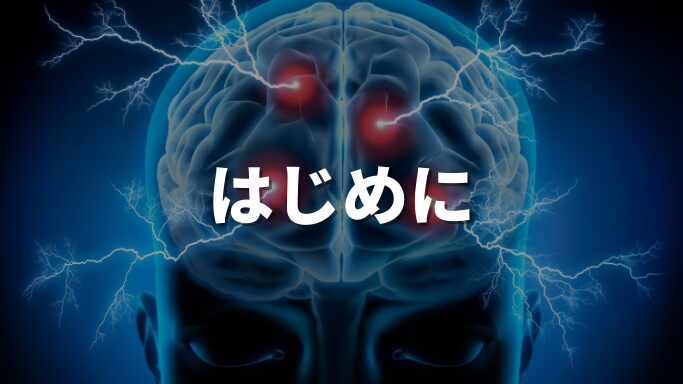
現代はスマートフォンやPCの長時間利用、情報過多によるストレスなど、脳に負担をかける要素が増えています。
そんな中で「脳を活性化する習慣」を身につけることは、集中力や記憶力の向上だけでなく、人生全般のクオリティを高めるために不可欠です。
この記事を最後まで読むと、脳を元気に保つための具体的な方法が分かります。
2.脳を活性化する習慣とは?

脳を活性化する習慣とは、脳の健康を維持・向上させるために日常生活で取り入れる行動や考え方を指します。
たとえば有酸素運動やバランスの良い食事は、脳への血流増加や必要な栄養素の補給につながり、認知機能をサポートします。
また、十分な睡眠や定期的な休息は、脳が情報を整理し新しい記憶を定着させるうえで欠かせません。
さらに、スマートフォンやPCなどのデジタル機器を使いすぎると、脳に過剰な刺激や疲労を与えがちです。こうした環境の中で、意識的に「脳にやさしい習慣」を取り入れることが重要視されています。
脳を活性化する習慣を続けることで、集中力や記憶力だけでなく、生産性や創造性の向上も期待できます。
3.脳を活性化する習慣のメリット・効果
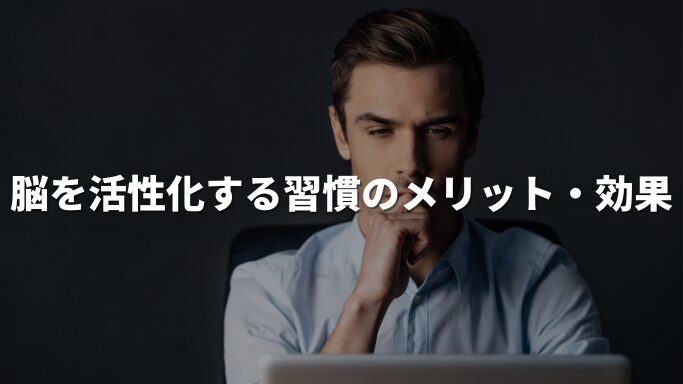
脳を活性化する習慣を身につけると、下記のようなメリットや効果が得られます。
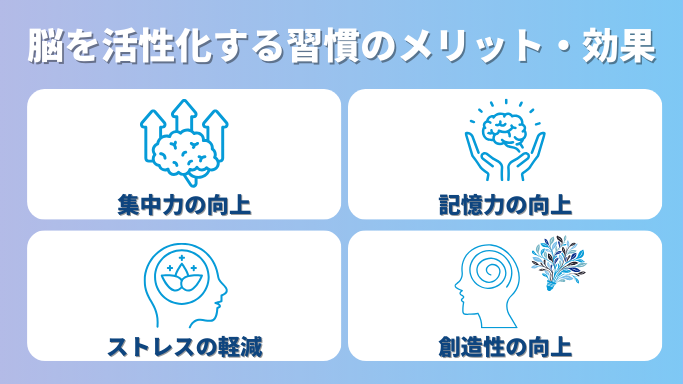
3.1.集中力の向上
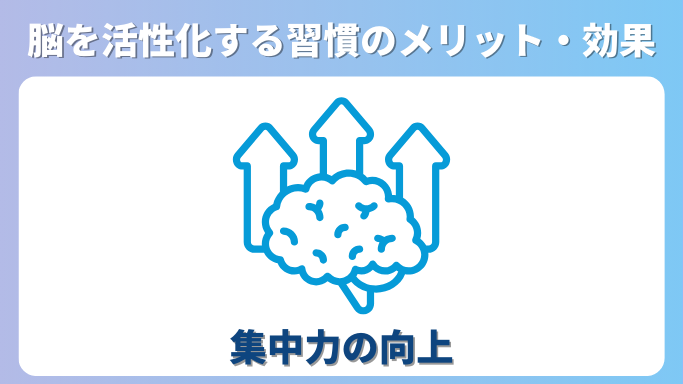
定期的な運動やストレッチ、適度な休憩を挟むことで脳の疲労を軽減し、集中力が持続しやすくなります。結果として業務や学習の効率が高まり、ストレスの軽減にもつながります。
3.2.記憶力の改善
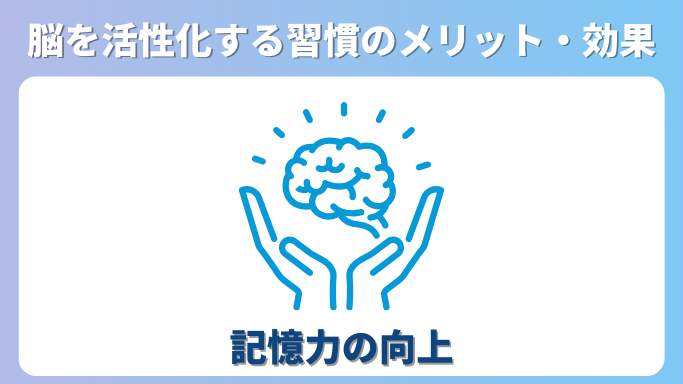
認知機能を維持・向上させる食事や新しい知識のインプットは、脳の神経回路を刺激し、記憶力をサポートします。特に高齢者においては、認知症予防の一環としても効果が期待されています。
3.3.ストレスの軽減
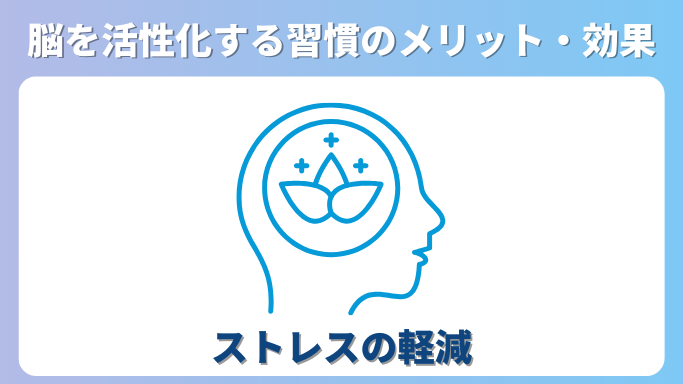
瞑想やマインドフルネスなどの習慣は、脳内でストレスホルモンをコントロールし、情緒の安定をもたらします。精神的な余裕が生まれることで、仕事や学習にもポジティブな影響を及ぼします。
3.4.創造性の向上

脳がリラックスした状態や、新しい刺激を受ける環境に身を置くことで、柔軟な発想やアイデアの着想が生まれやすくなります。組織やチームにおいてもイノベーションを促進する鍵となるでしょう。
こうしたメリットは、個人の生活だけでなく、仕事のパフォーマンスや周囲との人間関係にも良い影響を与えます。脳の健康を意識した生活習慣は、現代社会を生き抜くうえで欠かせない要素と言えるでしょう。
4.脳を活性化する習慣の具体的なやり方

ここでは、脳を活性化するための日常生活に取り入れやすい具体的な方法を紹介します。
4.1.有酸素運動を取り入れる

ウォーキングやジョギング、サイクリングなど、週に2〜3回、20〜30分程度の有酸素運動を行うと、脳への血流が増えて神経細胞の成長が促進されます。
また、朝の時間帯に軽めのウォーキングを習慣化すれば、一日のスタートをスッキリした頭で迎えられるでしょう。
4.2.脳に良い食事を意識する

オメガ3脂肪酸を含む魚(サバ、サーモンなど)や、抗酸化物質を多く含むブルーベリー、ビタミンEが豊富なナッツ類は「ブレインフード」と呼ばれ、脳機能の維持をサポートします。
糖分やカフェインの過剰摂取は一時的に脳が活性化しているように感じても、長期的には集中力や睡眠の質にマイナス影響を与える場合があります。適度な量を心がけましょう。
4.3.睡眠と休息をしっかりとる

1日7〜8時間程度の良質な睡眠は、情報の整理や記憶の定着に欠かせません。
仕事や勉強の合間にも短い休憩をはさみ、脳をリフレッシュさせましょう。
4.4.マインドフルネスや瞑想を取り入れる
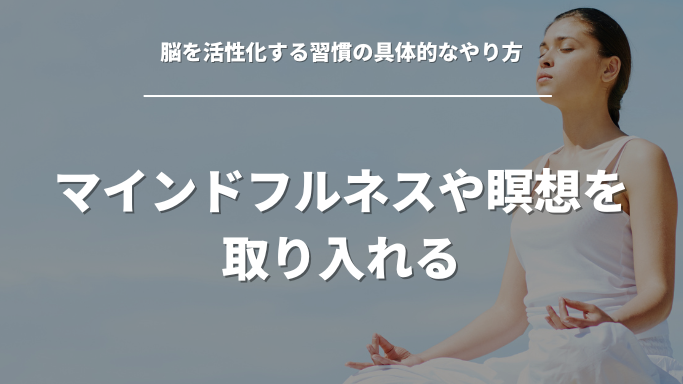
数分間の呼吸法や瞑想は、ストレスホルモンの分泌を抑え、脳を穏やかな状態に導きます。
朝や就寝前に1日5分〜10分程度行うだけでも、落ち着いた思考や集中力を保ちやすくなります。
4.5.新しいスキル・知的活動に挑戦する
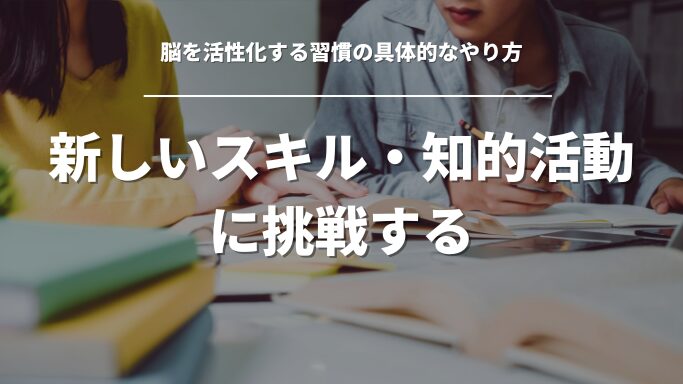
楽器の演奏や読書、パズル、語学学習など、新しい刺激を脳に与えることで神経回路を活性化します。
短時間でも継続することで、認知症予防や記憶力向上にも効果が期待できます。
これらの方法を自分のライフスタイルに合わせて組み合わせると、より効率的に脳を活性化できるでしょう。無理をせず、続けやすいことから少しずつ取り入れるのがコツです。
5.脳を活性化する習慣の注意点・デメリット
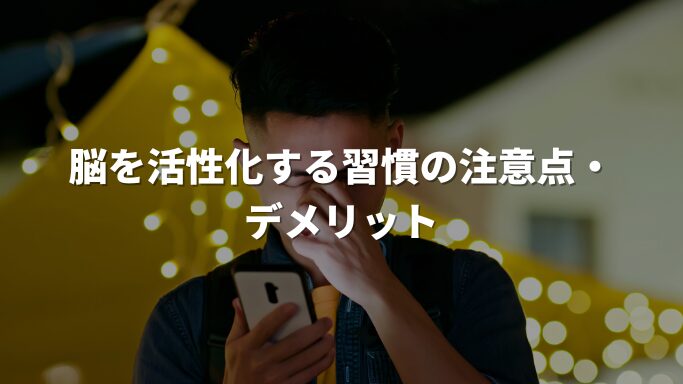
脳を活性化する習慣は多くのメリットをもたらしますが、実践にあたってはいくつかの注意点やデメリットも存在します。
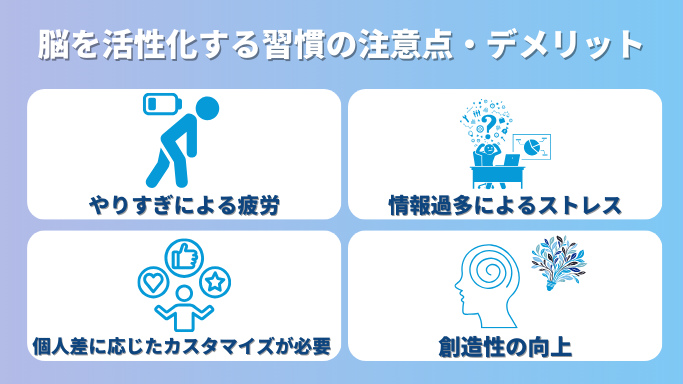
5.1.やりすぎによる疲労

運動や学習を過度に行うと、かえって脳や身体に負担がかかり、逆効果となる場合があります。適切な休息を挟みながら、バランスを取りましょう。
5.2.情報過多によるストレス
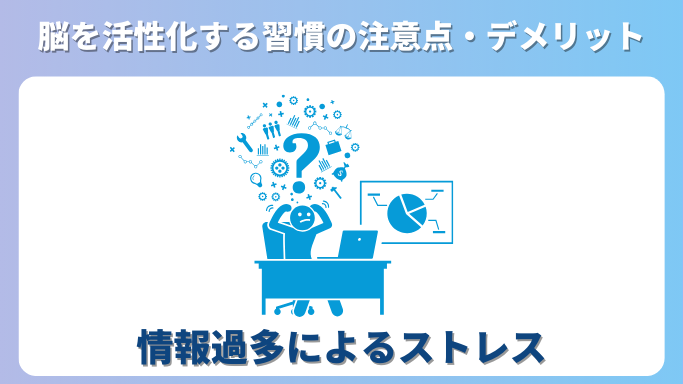
新しい情報やデジタル端末を使ったツールを詰め込みすぎると、脳が疲弊してしまうことがあります。必要な情報だけを厳選し、デジタルデトックスを取り入れる工夫が必要です。
5.3.個人差に応じたカスタマイズが必要
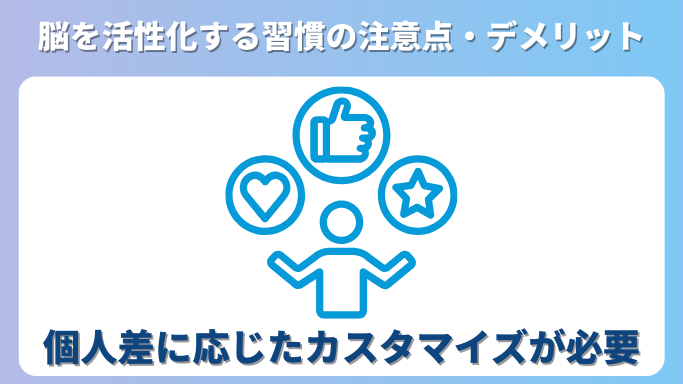
運動量や睡眠時間など、脳の反応や効果の出方は人によって異なります。自分に合わない方法を無理に続けると、ストレスや不調の原因になるので注意しましょう。
5.4.継続の難しさ

脳を活性化する習慣は、短期間では効果を実感しにくいケースもあります。モチベーションを維持し、長期的に取り組む姿勢が大切です。
6.脳を活性化する習慣の成功事例・実績

6.1.ビジネスパーソンの集中力向上

ある企業では、朝のミーティング前に10分間の瞑想タイムを設けることで、従業員の集中力と生産性が向上した事例があります。
短い時間でも瞑想を取り入れると、ストレスレベルが下がり、仕事の効率も上がる傾向が報告されています。
6.2.高齢者の認知症予防

地域のコミュニティで行われる「脳トレ教室」や「軽度の有酸素運動」は、高齢者の認知機能維持に役立つことが研究で示されています。
実践者からは、「友達と一緒に取り組むことで楽しく続けられる」という声も多く、社会的交流が脳の刺激になるというメリットもあります。
6.3.学生の学習効果アップ
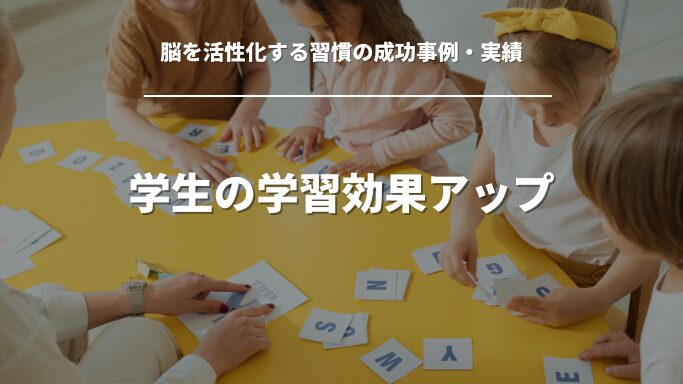
試験前や授業後に「軽いストレッチ」「短時間の散歩」「デジタルデトックス」を実践することで、学習効率が向上した学生もいます。
スマートフォンを一定時間オフにするだけでも、集中力が高まるとの報告があり、勉強時間の質が改善されることが期待できます。
こうした事例は、脳を活性化する習慣が実際の生活や学習、仕事の現場で有益であることを示しています。
ポイントは、無理なく継続できる方法を見つけることです。
7.まとめ
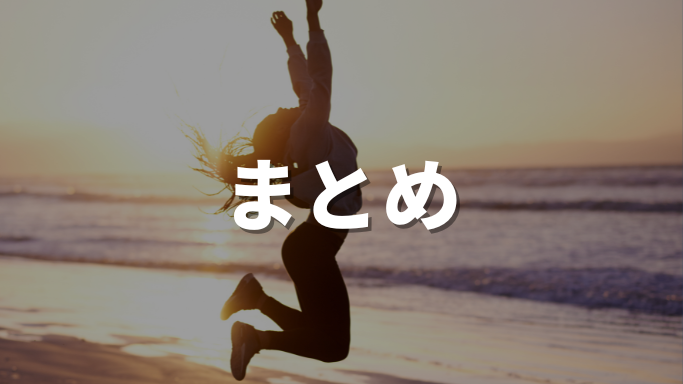
脳を活性化する習慣を日常に取り入れることで、集中力や記憶力の向上だけでなく、ストレスの軽減や創造性のアップも期待できます。
まずは、有酸素運動や瞑想など、自分に合う方法を一つ選び、無理なく続けることが成功の鍵です。スマートフォンの使い方を見直すデジタルデトックスも効果的なので、ぜひ今日から小さな行動を始めてみてください。
このブログでは他にも『脳』に関する記事を投稿しています。
興味があったら、ぜひチェックをしてみてください。↓